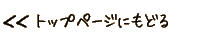バトルロワイヤル
土曜日の夜、『バトルロワイヤル特別編』を見た。どうしようかと迷ったのだが、なんかちょっと気分転換がほしいときに友人に誘われて行くことにした。気分転換にはちょっと強烈すぎる映画だったが、ここまでやると、もう行き着くところまで見たという感じで、地獄もここまでかなあと息をつくことぐらいはできた。
息子も友人の娘さんも小説で読み、学校でも話題になったということだけで、後は強烈なバイオレンスシーンがあるということだけしかしらなかった。バイオレンス苦手な私も、覚悟を決めて映画館に入った。(何で、覚悟を決めて入ったのかなあ?その日の朝方、映画のことはまだ考えもしなかったときに見た夢がなんか戦争のような感じだったことも影響しているかも・・)
現実にはあり得ないことだけど、高校生のあるクラス全員が殺人ゲームに巻き込まれる。最後の一人だけが生き残ることを許されるというゲームの時間の期限は3日間。それぞれにさまざまな武器を手渡される。もし、自分だったらという思いが少しはよぎるが、そんな思考を吹きとばすくらいの速さで殺人が繰り広げられ、アッという間に命が消えていく。
「これはヤバイ」誰だって、こんな映画を子どもに見せてはいけないと思うに違いない。しかし、物語の非現実感とは裏腹に描かれる子どもたち一人ひとりの生まれてきた背景のカルマのリアルさが、妙に現実感を帯びてくる。そして、北野たけし演じるこのゲームの首謀者である彼らのかつての担任の教師のみじめな心なども妙にリアルだ。
ヒットラーをスターリンをポルポトを思い出した。これまで国家とか政府とか独裁とか軍事政権とかの指導者の中に、限りなく正当化された殺人の数々を想起させられた。3日間が3年であったり、30年であったりしただけかも。
彼らは、自分の身近な人まで、疑惑と恐怖のうちに殺すことになっていった。殺す側は、いつか殺される側にまわるということ。疑うことは常に疑われているということ。いったんその選択をとったものの道は安心からはかけ離れていくのだ。たけし映画にもある容赦ないバイオレンスがここ深作映画にもあった。そして、そこからは、相反する絶対的信頼というものも浮かび上がってくる。男と女の愛情や友情のなかから、欲望やエロスをはぎとった絶対的な愛というものが彼らの描くバイオレンスの対局に最後に浮かび上がってくるような気がする。
No Comments Yet to “バトルロワイヤル”
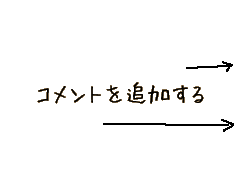

Revolt Basic theme by NenadK. | Entries (RSS) and Comments (RSS).| 管理画面|