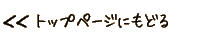学校は疲れるのはなぜ?
娘の学年は280人余り。7クラスだから40人くらい。学校というところは、巨大な工場のような規模だなあ。そりゃあ、こういうベルトコンベヤー式の説明会をしないと、かたずかないのだろうなあと想像は出来る。しかし、この高校入試の設定の仕方は、どういうことだろう。
私立の受験の発表はすんでいて、払い込みは今日22日中になっている。金額は30万くらいという大きなお金。公立が落ちたら、お金をおろして、そのまま私立高校に走るつもりだった。だから、書類はどちらも、まだ読んでいなかった。(普通はどちらも用意するモノのようだが(^_^;・・・)
受かったら、その日はイソガシイよ!って聞いてはいたが、よく考えたら、娘の行く学校の場所も知らなかったので、時間感覚もなかったのだ!だって、どこに行くのか、私が決めれることではないものね。
それに加えて、制服の事にしても、教科書のことにしても、なんて、優しくないのだろうと思った。娘の友達のお母さんは、母子で障害者の妹さんといっしょだったから、あんなに荷物があったら、本当に大変だっただろうなあ。
あんなにたくさんの教科書が本当に必要だろうか?あるいは、一度に渡してしまうのは仕事が早くかたづいていいだろうけど、少しずつ渡していくのがいいのではないのかなあ。おもりのように重い教科書のズシンとした重さは、日本の教育の今を物語っていた。本当に大切なものの重さは、目に見えるものではなく、もっと、もっと肌で感じて、ハートで感じていくことだって、みんなわかっているのに。
わかっている私も、とりあえず、娘に高校に入ることを勧めているという自己矛盾があるけれど、この行き場のない気持ちは、意識しておかなければなあ。
モモの家が、今ネットワークのなかで、家事援助や、子育て援助、障害者の人のサポートなどを試み始めたけれど、そこには、本当に丁寧なお互いの状況や性格や家庭の事情が理解できて、やっと始められたのだ。
学校というこの巨大な規模や教育産業の情報処理の方へのエネルギーの投入の状況からすると、何か途方もない距離を感じる。早い話が、娘の友人の妹さんが障害を持っていて、こんなふうに来るときに助け合うことすら考えられなかったという現実があるのだ。現代の学校にこそ、スローワークがいるのかもしれない。
No Comments Yet to “学校は疲れるのはなぜ?”
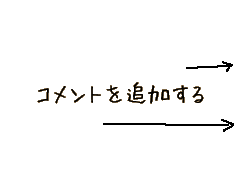

Revolt Basic theme by NenadK. | Entries (RSS) and Comments (RSS).| 管理画面|